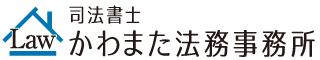宇都宮市東宿郷 お電話でのご相談・お問合せは
TEL.028-306-1605ブログ
blog
任意後見制度の8大リスク注意点とその対策方法
任意後見制度には、リスクや注意点も多々あります。安易に任意後見制度を選択していまわないよう、その対策方法としてどのようなことをしておけばいいのか、以下、詳しく解説します。
❶ 本人が行った契約の取消権がないのが基本
【注意】
任意後見制度では、本人の自主性を尊重する方針に基づいているため、基本的にですが、任意後見人が本人の代わりに行った契約を取り消す(取消権を行使する)権限がありません。この点は、成年後見人が持つ権限とは大きく異なります。例として、高齢者が営業マンのスムーズな話術によって不必要な商品を購入してしまった場合、任意後見人はその契約を取消すことができません。
【対策:取消権を代理権目録に明記し、消費者契約法など他の法律によりカバーする】 任意後見制度においては、本人の代わりに契約を取り消す権限がないため、他の法的手段を考慮する必要があります。任意後見契約の代理権目録に、各種取消権行使の条項を明記しておくことも一つの方法です。具体的には、民法における詐欺や脅迫、消費者契約法に基づく不公正な取引条件などを主張して、契約を取り消すことができるように対策をしておきます。
❷ 任意後見利用の費用負担が大きい
【注意】
任意後見制度を利用するには一定の費用がかかることは避けられません。特に、任意後見制度利用時と、任意後見監督人の報酬が発生するため、費用的な負担が発生します。
任意後見利用時の費用と任意後見監督人への報酬が必要
任意後見制度利用にあたっては、任意後見契約書作成時と任意後見監督人選任申立時に初期費用がかかります。
また、任意後見人・任意後見監督人にはその業務の対価として報酬が支払われることがあります。任意後見人の報酬は契約によって自由に設定することができますが、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が定めます。専門性が求められるこの役割には、しばしば弁護士や司法書士、社会福祉士などが選任されるため、その報酬が定期的にかかります。
対策:任意後見人の報酬を契約で決めておく
【対策】
費用を抑制するための一つの方法は、任意後見人の報酬を事前に明確に契約で決めておくことです。特に、無償で引き受けてくれる信頼できる人がいる場合、無報酬である旨を契約に明記しておくと良いでしょう。
他方、任意後見監督人の報酬は避けられない場合が多いですが、任意後見監督人の報酬は一般的には管理財産の額によって報酬が変動するので、その点も考慮に入れた上で計画を立てると良いでしょう。
任意後見監督人の報酬の相場は、管理対象となる財産の額によっても異なります。具体的には以下のようになります。
・管理財産が5000万円以下の場合:月額5,000円~20,000円
・管理財産が5000万円超の場合 :月額25,000円~30,000円
❸ 死後の財産管理ができない
【注意:任意後見は生前の財産管理が対象】
任意後見制度は生前の財産管理の面で有効ですが、その範囲には明確な制限があります。その一つが、任意後見契約が本人の生存中にのみ有効であるという点です。すなわち、本人が亡くなると、任意後見契約は自動的に終了し、その後の事務処理や財産の管理については任意後見人の責任範囲外となります。
任意後見契約が終了すると、本人が生前に管理していた財産は、法定相続人へ引き渡すプロセスが始まります。この段階で、任意後見人が関与することはできません。特に遺言がない場合、相続人間での遺産分割協議が必要になり、これが新たな手続きと時間を必要とします。
【対策】死後の事務は死後事務契約や遺言、家族信託で対応する
このような制約を考慮すると、死後の財産管理や事務処理については、任意後見契約以外の手段を考える必要があります。具体的には、「死後事務委任契約」や「遺言」、または後述する「家族信託契約」などが有用です。これらの手段を通じて、本人の意思に沿った形での財産の引き継ぎや、スムーズな事務処理が可能になります。
❹ 第三者の監督を受ける必要がある
【注意:監督人は第三者である専門家がつくことが多い】
本人の判断能力が低下し、任意後見制度を開始する際には、任意後見監督人が必ず選任されます。この監督人の主な役割は、任意後見人が本人の代わりに適切に財産管理や生活支援を行っているかを確認することです。
専門的な知識が必要な任意後見制度において、監督人はしばしば弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が担当します。特に家庭裁判所が任意後見監督人を選任する際、家族が任意後見人となっているケースでは、中立性を保つために第三者である専門家が選ばれることが一般的です。
【対策任意後見監督人の候補者を立てる】 任意後見監督人については、一定の制限を除いて、任意の人物を候補として申し立てることが可能です。しかし、実際に誰が選任されるかは、家庭裁判所の判断に依存します。したがって、信頼できる専門家を事前に調査し、候補者として提案することがおすすめです。
このような事前の準備によって、もし家族が任意後見人となっても、任意後見監督人となる専門家との相性問題や意見の不一致などを予防することができます。
❺ 認知症発症後は契約できない
【注意:任意後見契約締結には判断能力が必要】
任意後見制度は事前に任意後見人を定めておくことができるのがメリットですが、問題点としては、任意後見契約が締結できるタイミングが限定されている点です。
特に、認知症やその他の理由で判断能力が低下した後には、任意後見契約を結ぶことは困難です。
任意後見契約を締結するには、契約者がその内容を理解し、自らの意思で合意できるだけの判断能力が必要です。認知症やその他の疾患で判断能力が低下してしまった場合、公証役場は医師の診断書を要求してくることがあります。この段階になると、任意後見契約の締結はほぼ不可能となります。
【対策】
このようなリスクを考慮すると、最も確実な対策は「元気なうちに事前に契約をしておく」ことです。
健康で判断能力に問題がない段階で、将来を見据えた任意後見契約を結ぶことで、判断能力が低下した後でも安心して生活を送ることができます。特に、任意後見契約は後述する家族信託と異なり、契約段階では任意後見人による財産管理は開始せず、本人が現状と変わらず財産を管理できるので、将来の万が一があった時の予防として、本人に導入を勧めやすいです。
❻ 判断能力喪失時に自動的には始まらない
【注意:任意後見監督人選任申立をしないと効力が生じない】
任意後見制度は事前の財産管理対策として有効ですが、注意しなければいけないのは、必要なタイミングで任意後見制度が自動的に発動するわけではないという点です。本人の判断能力が低下した場合でも、特定の手続きを踏まないと任意後見の効力は発生しません。
任意後見制度においては、任意後見契約を結んだだけでは任意後見の効力は発生しません。特に、将来型の任意後見契約を締結していたとしても、家庭裁判所に任意後見監督人選任申し立てを行わない限り、その効力は発生しないのです。
この申立手続きには、時間と手間が必要とされ、さらに任意後見監督人が正式に選任されるまでには申立から2〜3週間の時間がかかる場合もあります。
【対策:見守り契約や財産管理委任契約で任意後見監督人申立を義務化する】 このような状況を避けるためには、事前に見守り契約や財産管理委任契約を締結しておくことが有用です。
これにより、本人の状態が変わったときに早めに気づき、適切な手続きを取ることが可能になります。また、これらの契約に「任意監督人の選任請求義務」を明記しておくことで、任意代理人が本人の判断能力喪失後も任意後見監督人を選任する義務が生じ、後見のスムーズな運用が期待できます。
❼ 契約書に記載のない事項は対応不可
【注意:任意後見人の代理権の範囲は代理権目録の記載に限定】
任意後見人の権限の範囲には一定の制限があります。特に、任意後見人の代理権は、契約文書で明示的に指定された項目に限定されます。そのため、未記載の事項については後から追加することが難しく、この点が任意後見制度の限界とも言えます。
任意後見契約において、いわゆる「代理権目録」の中で、任意後見人が持つ代理権の範囲が詳細に記されます。この目録に含まれない事項については、任意後見人が単独で行動することは認められません。
したがって、不足する項目に後から気づいた場合、特に本人の判断能力が既に低下している場合、新たに任意後見契約を締結することはできません。
【対策:ライフプランをつくり、事前にどんなことを任せるのか決めておく】
このような問題に対処するための最良の方法は、事前に慎重にライフプランを作成し、どのような事項について代理権を持たせるのかを明確にしておくことです。これにより、未来の不確実性に備え、必要な代理権を事前に網羅することができます。
❽ 一度始めると解約が難しい
【注意:任意後見監督人選任後は家庭裁判所の許可がなければやめられない】
任意後見制度はいったん任意後見人による財産管理を始めた後に終了することが非常に厳格に制限されています。特に、任意後見監督人が選任された後は、制度を終了するには家庭裁判所の許可がなければ、やめることができません。
任意後見制度が一度始まると、特に任意後見監督人が選任された後には解除の手続きが厳格になります。この段階での解除には家庭裁判所の許可が不可欠となり、その許可を得るためには「正当な理由」が必要です。審査は本人の安全と保護に重点が置かれ、解除をしても問題ないかなど、多角的に評価されます。
正当な理由として考えられるケースは、
・任意後見人が健康上の問題で任務を継続できなくなった場合
・任意後見人が転居や転職で遠隔地に移り、十分なサポートが難しくなった場合
などがあります。このような状況が生じた場合には、家庭裁判所の許可を得て任意後見契約を解除することができますが、その過程は通常煩雑で時間もかかることが一般的です。
【対策:任意代理人としての財産管理状況を見て、相性があわなければ解除する】
任意後見制度の適用を考慮する際、任意後見監督人が正式に選任される前の段階で、任意代理人として行動する人物の適性や財産管理状況をしっかりと評価することが賢明です。この段階であれば、公証人の認証を受けた書面を用いて、比較的容易に契約を解除できます。
具体的な手段としては、まず任意代理人として財産管理やその他のサポート活動を一定期間行ってもらうことで、その人物がどれほど適切な業務を行えるか、また、本人や家族との相性が良いかを確認することができます。この評価が不十分であれば、公証人の認証を受けた書面で解除が可能です。その際には手数料がかかることも覚えておきましょう。
任意後見制度の代替手段:家族信託との比較 高齢化が進む社会では、認知機能が衰えたり財産をどのように管理するかが問題になっています。任意後見制度以外で事前に安全策を講じる手段として、家族信託が増えており注目を集めています。ぜひ、家族信託も併せてご検討ください。
ご相談は随時お受けしております。
※見積りのご相談は固くお断りいたします。
【ご相談について】
月曜日~金曜日:午前10時~12時まで/午後1時~5時まで
土曜日は、ご予約済みの法律相談のみ承ります。
【ご相談費用】
業務をご依頼いただいたうえでのご相談の場合
ご相談費用は、無料とさせていただきます。
ご相談のみ場合
1時間あたり平日:5,500円(税込)・土曜日:11,000円(税込)のご相談費用をいただきます。