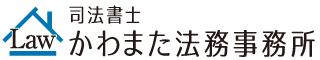宇都宮市東宿郷 お電話でのご相談・お問合せは
TEL.028-306-1605ブログ
blog
信託を活用した融資の基本~信託内借入と信託外借入の2つの違い
☑家族信託・民事信託を活用した融資には①信託内借入と②信託外借入の2つの方法がある。
☑信託内借入は受託者が借入を行い、信託財産に借入金が帰属し、一貫して受託者名義で財産管理を行うことができる。
☑信託外借入は、親(委託者本人)が借入を行い、建築手続きを行う必要があるため、親が元気な時に融資などを行う必要がある。
☑信託内借入と信託外借入では受益権の移動時における考え方が異なる。
☑信託融資に対応できる金融機関も実務の取り扱いもまだ少なく、不透明な部分が多い。 家族信託・民事信託を活用すれば、融資や建築なども受託者の権限で自由にできると思われている方が多くいますが、実際に融資などを伴う金融実務の実例数は少なく、実務動向も不透明な部分があるのが現状。
以下、詳しく説明します。
信託を活用する際の融資パターンは2つ
生前対策業務を手掛ける専門家でもよく誤解をされている方が多いですが、家族信託・民事信託は成年後見制度のような代理人制度ではありません。
受託者は信託された財産(信託財産)の管理権限しかありません。
成年後見人は代理人なので、成年後見人が行った法律行為は本人に当然に効果が及びますが、受託者はあくまで信託された財産についての管理処分権限しか有しません。そのため、融資を取り扱うに際しても、信託契約で定めた受託者の権限にもとづき、融資を行うのか(信託内借入)、それとも委託者本人(信託外借入)で借入を行っていくのか検討していく必要があります。
受託者が行う融資手続きである信託内借入
信託内借入とは受託者が信託契約で定めれた借入権限をもとに、融資を行う方法です。
受託者の権限で借り入れた金銭は、信託財産の中に組み込まれることから信託内借入といいます。
受託者が借り入れた借入金は、信託財産の中に融資(借入金)が組み込まれます。
信託内借入では、信託財産の中に融資金があるので、受託者は信託財産に組み込まれたその融資金(金銭)を活用して、アパート建築手続きを行っていきます。
信託財産である金銭を元に建築しているので、完成後のアパートは当然、信託財産です。アパート完成後は、信託財産である建築後のアパート収入を原資として、信託財産から借入金の返済をおこなっていきます。
委託者本人が融資を受ける信託外借入
受託者が信託契約で定めた権限で借り入れを行う信託内借入に対して、信託外借入は親(委託者本人)が借入を行います。
つまり、信託契約の枠外で親(委託者本人)が金融機関で融資手続きを行い、融資金(金銭)は信託財産にはならず、親本人の借金となることから、信託外借入と呼ばれます。
そして、親(委託者本人)自身が融資金を活用して、アパートを建築し、親名義でアパート建築後、受託者である子供に建物を信託しますこれが信託外借入です。あくまで親名義で借入、親名義で建築が信託外借入です。
債務は親に残したまま、親が借り入れた金銭のみを先に受託者に信託し、信託された金銭を活用して受託者が建築し、新築アパートをそのまま信託財産とするというスキームもあります。
いずれにしても、信託契約の枠外で融資はあくまで親(委託者本人)が手続きを行うということがポイントです。
信託内借入と異なり、信託外借入では、新築アパートとアパート収入は信託財産となりますが、借入金は親の名義のままの状態です。そのため、ローンの返済は親(委託者本人)が行っていく必要があるため、信託財産として入ったアパート収入から随時、借入金返済資金を親(委託者本人)に送金するというお金の流れを考える必要があります。
借入手続きをあくまで親(委託者本人)自身に行っていただく必要があるため、親が元気な時に建築・融資計画を遂行していく必要があります。
信託内借入と信託内借入では受益権の移動における取り扱いが異なる
信託内借入では、受託者が借入権限をもっていることから、受託者名義で融資、建築手続き、返済手続きまでを一貫して行うことができ、すべて受益権(信託財産)の中に含まれます。
そのため、相続などによる受益権の移動があっても、信託財産に組み込まれているアパートなどのプラスの積極財産とともに借入金などマイナスの消極財産も一緒に動くので、財産承継は受益権を中心に考えればよいことになります。
信託内借入と異なり、信託外借入では、信託財産の中に、融資(債務)が組み込まれていないんため、委託者兼受益者の死亡時など受益権移動時に、受益権(積極財産)の移動と債務(消極財産)の移動が違う動きをするので注意が必要です。
受益権が信託契約で定めた第二受益者等に移動しますが、債務は信託財産に組み込まれていないため、法定相続されます。
そのため、第二受益者が法定相続人であれば相続後の債務も法定相続で承継されますが、(法定相続人が複数人いる場合は別途債務引受が必要です)第二受益者等が法定相続人でない場合には、受益権(積極財産)は第二受益者等に移動し、債務(消極財産)は法定相続人に承継されることになるのです。
つまり、財産を受け継ぐ人にローンが帰属しないという状態がおこります。
そのため、金融機関も信託外借入を行うにあたっては、第二受益者等が法定相続人かどうか、など確認していますし、実際に組成する際も、信託内借入でいくのか、信託外借入でいくのか、中に債務をいれるのか、いれないのかという判断を含めて検討が必要になってきます。
信託内借入と信託外借入では、相続時の相続税評価における債務控除の考え方も検討する必要があります。
信託融資に対応できる金融機関は多くない
2019年8月現在では、家族信託・民事信託に対応した融資や信託で管理する金銭管理口座の開設に対応できる金融機関がまだまだ少ない状況です。
実際に信託を活用した融資、アパート建築手続きを行いたいと考えていても相談した金融機関では取り扱いができなかったり、たとえできたとしても信託外借入、信託内借入いずれかの方法を活用しないといけない、そして、融資のための融資条件が通常のアパートローンなどよりも厳格に審査され、一般的な融資条件よりも多くの担保や保証人を求められる可能性があります。
更に、2020年4月1日からは債権法が改正され、事業用融資については保証意思宣明公正証書の作成が必要となりましたので、留意が必要です。
ご相談は随時お受けしております。
※見積りのご相談は固くお断りいたします。
【ご相談について】
月曜日~金曜日:午前10時~12時まで/午後1時~5時まで
土曜日は、ご予約済みの法律相談のみ承ります。
【ご相談費用】
業務をご依頼いただいたうえでのご相談の場合
ご相談費用は、無料とさせていただきます。
ご相談のみ場合
1時間あたり平日:5,500円(税込)・土曜日:11,000円(税込)のご相談費用をいただきます。