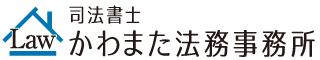宇都宮市東宿郷 お電話でのご相談・お問合せは
TEL.028-306-1605ブログ
blog
認知症による預金口座の凍結を防ぐには
「認知症と診断されたら銀行口座が凍結されるらしい」「本人の介護費用や生活費も引き出すことができなくなるようだ」という話を聞いたことはないですか?
認知症の親の介護をする子世代にとって、最も気になる問題の一つがお金についてでしょう。「銀行に知られなければ親のキャッシュカードを使っていてもいいですよね?」という質問もよく受けます。
確かに、暗証番号さえ知っていれば誰でも預貯金の引き出しをすることは可能ですよね。
今回は、家族による引き出しのリスクも含め、後ろめたさや不安を感じてはいるものの、具体的な対策を講じていない方が非常に多い「口座凍結」について、解説していきます。
※本文中、銀行などの金融機関全般について、便宜上「銀行」と記載しております。
今回のポイントは次のとおりです。
☑銀行口座が凍結されるタイミングは、口座名義人の死亡時と銀行取引の中で認知症により本人の判断能力が著しく低下したことを銀行が知ることにより凍結される可能性がある
死亡による口座凍結は銀行全取引が停止するが、認知症による判断能力低下は一部の取引が制限され、入出金、振込、口座解約などができなくなる
☑判断能力の著しい低下によって引き出しができなくなった口座(口座凍結)を解凍するには、法定後見制度を使うのが原則
☑口座凍結を未然に防ぐ方法がある!
・銀行のシステムの中での対策
・任意後見制度の利用
・家族信託制度の利用
☑口座凍結を予防し、本人のために適切に使う仕組みづくりができるのは、本人の判断能力が「著しく低下していない」段階のみ。認知症だから・・・とあきらめるのはまだ早いかも!?
☑親の預貯金を勝手に使う一番のリスクは相続人間の争いを招くことである
今回は、認知症で口座凍結するとどのような状態になるのか?
そして、どんな方法で口座凍結に備えることができるのか、親の口座を引き出し、管理するために最善の対策方法をお伝えします。
1.親が認知症になって困る「口座凍結」とは?
近年、認知症による判断能力の低下によって、金融機関で払出し等の取引ができなくなるケースが多くなっています。親が認知症になった時に事前の対策ができていないと、預金の引き出しに制限がかかってしまい、生活費や医療費用などの払出しができなくなってしまう可能性があります。
1‐1.口座凍結されるタイミングは?
銀行が口座を凍結する要因として、”口座名義人が死亡した場合”と”認知症などによる判断能力が著しく低下した場合”があります。凍結といっても、それぞれの要因ごとに銀行取引が制限されるタイミングと制限の内容が異なります。
①口座名義人が死亡した場合
預金の口座名義人が死亡した場合、銀行は死亡の事実を知ったタイミングで、その口座名義人の同銀行内にある全ての口座を凍結します。ATMでの入出金、振り込みや口座引き落とし、通帳の記帳など、全ての銀行取引ができなくなる「凍結」です。
口座名義人について相続が発生すると、故人の預金口座は相続人全員の共有財産となります。その後、相続人全員による遺産分割協議を経て誰が預金口座を相続するのか決める手続きをし、預金口座の名義人が定まります。そのため、亡くなった口座名義人の戸籍収集や法定相続人全員による遺産分割協議等の全ての相続手続きを済ませ必要書類を提出しなければ、預金口座の解約、相続人への払い戻しが出来ません。
②認知症などによる判断能力が著しく低下した場合
すでに認知症が進み、判断能力がかなり低下している場合、銀行がその事実を知れば「口座取引を大幅に制限」します。これがよく言われる、認知症による口座凍結という問題です。
1‐2.認知症により口座凍結されるとどうなる?
まとめると認知症の場合の口座凍結は以下のようになります。
①銀行窓口で各種手続きができなくなる
振込や払出しはもちろんですが、その他、定期預金の解約・契約、カード・通帳等の紛失・再発行、口座振替、投資信託の購入・解約、融資や借換等の手続きができなくなります。
②ATMの入出金は基本できない
もちろん、口座凍結されてしまうとATMからも入出金はできません。
銀行側にバレないように親の代わりに預金を引き出していたとしても、連続で限度額いっぱいまで立て続けに引き出すなど、使い方が明らかに異常だと判断された場合は本人に状況確認などの連絡がなされる場合などもありますので、注意が必要です。
【重要】認知症によって口座凍結される場合、全ての取引ができなくなるわけではない
口座を凍結されると、前述の通り預金の引出し、入金、定期預金の解約など口座を使った銀行取引ができなくなります。しかし、死亡時のように、全取引の停止=「口座凍結」とはなりません。
口座からの自動引落としや他口座からの振込み(家賃の支払いを受け取る、配当金を受け取るなど)はそのまま続けられますが、払い戻しや契約内容の変更はできなくなる、というイメージです。
1‐3.口座凍結される大きな影響
①介護費用や生活費の支払いが子どもの負担になる
口座凍結になって多くの方が困るのが、認知症になった親のお世話をするための費用や病院代、生活費などを引き出す事ができないことです。
亡くなるまでの介護期間が長くなることも多く、そうなると子ども自身の出費に加えて親の介護費用もとなると、生活が困窮することは目に見えており、その間名義人本人の口座から年金や貯金が下ろせないのは非常に困ります。 ②年金受取口座の変更手続きができない
年金振込がある場合、認知症による口座凍結では振込は制限されませんので、引き出せない口座内に年金がたまっていくことになります。親の生活費を年金に頼っている方であればあるほど、もし年金受取口座が凍結されると、困ったことになってしまいます。
さらには、年金受取口座は、原則としてご家族で変更手続きができません。
2.口座凍結を解除するには、成年後見制度しか方法がない
すでに認知症が進み、判断能力がかなり低下している場合、銀行が事実を知れば口座取引に制限がかかります。以後払い戻し、契約内容の変更(定期預金の解約など)は、家族であってもすることはできません。
2‐1.成年後見制度とは?
この制限を解除するには、基本的には、成年後見制度を使う以外方法がありません。つまり、本人のために、本人の財産を管理する法定代理人として成年後見人の選任の申立てをするのです。最高裁判所事務総局家庭局の統計では、令和3年の成年後見人の選任の申立ての動機第一位は断トツで預貯金の管理・解約をするためとなっています。
2‐2.成年後見人に家族が選ばれる可能性は?
成年後見人の選任は、民法で定める欠格事由に該当しない者の中から家庭裁判所が決定し
【後見人の欠格事由】
民法第847条
次に掲げる者は、後見人となることができない。
1. 未成年者
2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
3. 破産者
4. 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5. 行方の知れない者
成年後見人になるための特別な資格はありません。家庭裁判所が法定後見人の候補者の中から、誰が相応しいかを判断し、選任する仕組みです。そのため、たとえ親族であっても、家庭裁判所が相応しくないと判断すれば法定後見人にはなれません。
親の財産を管理するために親族を成年後見人に選任したいと考え申し立てをしても、成年後見人に親族が就けるとは限りません。裁判所の統計資料によると、親族以外の専門家等が全体の8割就任しています。金融資産が多い方などは仮に親族が就任できた場合でも、後見監督人として専門職を就任させる、または、日常生活に必要な預貯金以外は全て家庭裁判所の指示がないと引き出しができない「成年後見制度支援信託」や「成年後見制度支援預金」の制度の利用を求められることが多いです。
これは、本人の財産の適切な管理と相続人間での争いを未然に防ぐため、中立な第三者による管理とご家族が自由に引き出しができないような仕組みをつくることを目的にしています。
2‐3.成年後見制度を利用する不便な点
①成年後見人を専門家が担う場合は毎月の報酬を支払い続ける必要がある
仮に専門職後見人が就任した場合、報酬が発生し、月2~5万円(総資産による)となり、本人が亡くなるまで続きます。
認知症は、発症してから亡くなるまでどのくらいの期間になるかがわかりません。成年後見制度は途中で解約することもできませんので、その間、報酬を支払い続けることになり、負担も大きくなります。
②成年後見人の選任には時間がかかる
また、法定成年後見人の選任の申立てから選任までに通常数か月かかるので、凍結解除までにはそれなりに時間を要します。そのため、引き出したいと思ってもすぐに引きだす事ができないのは非常に厄介です。
③家族の判断だけで自由につかえない
成年後見制度は本人の財産を守るための制度ですので、基本的にどんな支出をしたのか記録して家庭裁判所に管理状況を報告することになります。本人の財産を減らすリスクのある行為は基本的に認められないので、ご家族が「こう使いたい」と考えていたとしても、その通りにできるとは限らず、柔軟な財産管理はできないでしょう。
そのため、出来れば、この段階に至る前に(判断能力がまだ、ある段階で)何らかの対策を講じておくことが望ましいと言えます。
当事務所では、預金が凍結されてしまいお金の管理ができなくなった方、現在キャッシュカードで認知症の親の預金管理を行っている方へ、今後どのように財産管理の仕組みをつくればいいのか、相談対応をせていただいております。どのような対策が今ならできるのかアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
ご相談は随時お受けしております。
※見積りのご相談は固くお断りいたします。
【ご相談について】
月曜日~金曜日:午前10時~12時まで/午後1時~5時まで
土曜日は、ご予約済みの法律相談のみ承ります。
【ご相談費用】
業務をご依頼いただいたうえでのご相談の場合
ご相談費用は、無料とさせていただきます。
ご相談のみ場合
1時間あたり平日:5,500円(税込)・土曜日:11,000円(税込)のご相談費用をいただきます。